ひっさしぶりにMBTI診断やってみたら、ISFPに変わってた☹️
— みさき (@mi_chas2_) July 29, 2025
でも特徴読むと1番当たってるのでは…?ってなってる☹️ pic.twitter.com/e4Bi9k85I3
近年、SNSやメディアで「MBTI診断」という言葉をよく耳にするようになりましたね。
まるで血液型占いや動物占いが流行ったように、自分の性格タイプを知ることで、自己理解を深めたり、人間関係を円滑にしたいと考える方が増えているようです。
しかし、「MBTI診断 どれがいい?」と検索する中で、公式MBTIと、ネットで手軽にできる16Personalitiesのような診断テストとの違いに戸惑う方も少なくないのではないでしょうか。
それぞれの信頼性や、日本人に多い性格タイプ、さらには「性格が悪い」と言われるタイプは本当に存在するのかといった疑問について、本記事が皆さんの理解を深める一助となれば幸いです。
- 正式なMBTIと16Personalitiesには明確な違いがある
- MBTIの科学的信頼性には様々な意見があり、利用には注意が必要
- MBTIは自己理解や他者理解を深め、可能性を広げるツールとして活用できる
- 性格タイプに関するランキングは「違い」を示すものであり、優劣ではない
「MBTI診断どれがいい?」その前に知るべき「公式」と「流行り」の違い
- MBTI診断と16Personalitiesの決定的な違いとは?
- 流行のMBTI診断に隠された「信頼性」の真実
- 「公式MBTI」を受けることの本当の意味とメリット
- MBTIと16Personalities、どちらを選ぶべきか?
- MBTIの誤解と社会への影響
MBTI診断と16Personalitiesの決定的な違いとは?
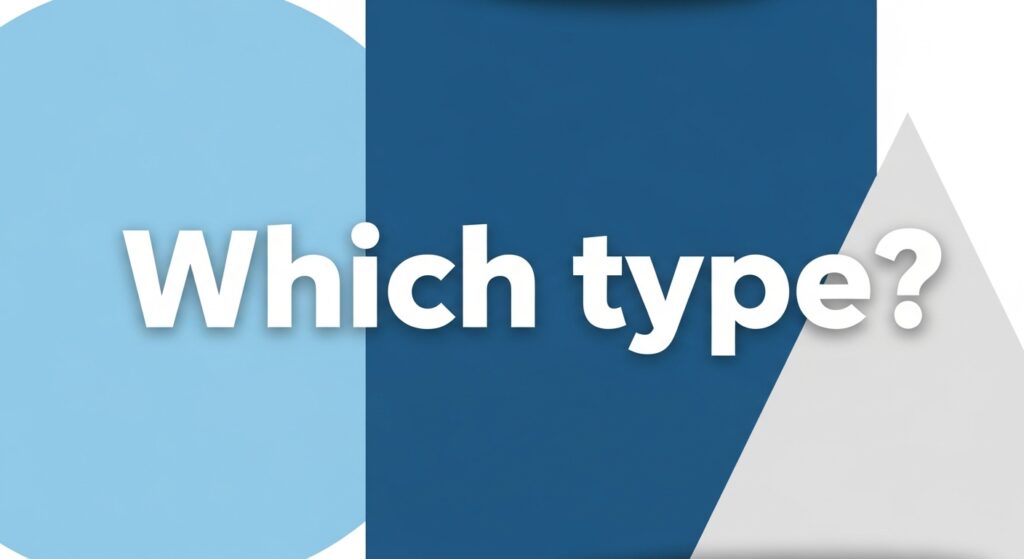
「MBTI診断 どれがいい?」と考える際に、まず知っていただきたいのが、現在ネット上で広く流行している「16Personalities」と「正式なMBTI」には明確な違いがあるという点です。
多くの人が「MBTI」だと思って楽しんでいるウェブテストは、実は「16Personalities」という、MBTIを模して作られた別の診断ツールなのです。
正式なMBTIは、心理学者C.G.ユングの理論を基盤とした性格検査であり、その大きな特徴は、有資格者(認定ユーザー)によるフィードバックとセットでなければ受けることができないという点です。
日本では2000年から資格制度が導入されていますが、まだ認知度が低く、手軽にできる16Personalitiesに市民権を奪われてしまっているのが現状です。
正式なMBTIは、単なるWeb検査の結果をタイプとするのではなく、フィードバックを通して自他の違いを体感し、最終的に「最もシックリくる性格タイプを自己選択」するというプロセスを重視しています。
これは、Web検査の結果が自己探究の旅の「切符」に過ぎず、最終的な「自分のタイプ」は自分自身で選択するというMBTIの本質を示しています。
一方、16Personalitiesは、Web上で無料で手軽に診断できるため、中高生にまで広く浸透しつつあります。
しかし、その手軽さゆえに、本来のMBTIの意図とは異なる誤った解釈や使われ方がされ、まるで本物のMBTIのように誤認されてしまうケースが多く見られます。
例えば、診断結果だけで性格の良し悪しや能力の高低、適性の有無を断定したり、相性を判断したりする傾向があるようですが、正式なMBTIは、性格の良し悪しや能力の高低、適性の有無を示すものでは決してありません。
あくまで性格の違いを示すものなのです。
さらに、日本ではMBTIは商標登録されており、認定ユーザー以外の者が「MBTI」の名称を無断で使用することは、商標法上の侵害となる可能性もあるとされています。
このように、手軽さの裏には、誤解や誤用、そして法的な問題まで潜んでいる可能性があるため、両者の違いを理解することは非常に重要です。
流行のMBTI診断に隠された「信頼性」の真実

MBTI診断について考える際に、多くの人が気になるのが、その診断の「信頼性」ではないでしょうか。
巷で広く使われている性格診断ツールであるMBTIですが、その科学的な妥当性については、長年にわたり多くの議論が交わされています。
まず、科学界からは、MBTIが「疑似科学(pseudoscience)」であるという厳しい指摘が数多く存在します。
これは、MBTIを支持する研究の多くが、MBTIを運営する団体自身によって行われ、その専門誌に掲載されているため、独立性や偏りの問題が指摘されていることに起因します。また、多くの研究が、その方法論において「科学的ではない」と見なされている点も、信頼性が疑問視される理由の一つです。
具体的な問題点としては、「低いテスト-再テスト信頼性」が挙げられます。これは、同じ人がわずか5週間程度の期間を空けてMBTIを再受検した場合、約半数(39%から76%)が異なるタイプに分類されてしまうというものです。つまり、一度受けた結果が、次回も同じになるとは限らないため、個人の性格を「固定的なタイプ」として捉えることの妥当性に疑問符がつけられます。
さらに、MBTIの根本にある「二分法(dichotomies)」、例えば内向型か外向型か、感覚型か直観型かといった分類についても批判があります。
多くの研究では、これらの特性は二つの明確なカテゴリに分かれるのではなく、正規分布のような連続的なスペクトル上に存在し、ほとんどの人が中間に位置することが示されています。
しかし、MBTIでは強制的にどちらかのタイプに分類するため、実際にはほとんど差がない人々が異なるタイプとして扱われてしまうという問題が生じます。
心理学の専門家たちも、MBTIの信頼性について懸念を表明しています。心理学者のアダム・グラントはMBTIを「消えない流行(fad that won’t die)」と呼んでいます。
これは、MBTIの結果が、バーナム効果(誰にでも当てはまる漠然とした記述を、自分だけに当てはまると感じる心理効果)や、お世辞、確証バイアスといった心理現象に依存しているため、多くの人が「当たっている」と感じやすいという側面があることを示唆しています。
これらの点から、特に就職活動や採用選考のスクリーニングツールとしてMBTIを使用することは、その開発元であるMyers-Briggs Company自身も「不適切」であると表明しており、強く非推奨されています。
企業が流行に乗って16Personalitiesを導入した結果、混乱を招いたり、タイプによって不当な判断を下したりする事例も報告されています。診断結果を過信することで、自分や他人の可能性を不必要に狭めてしまうリスクも指摘されています。
したがって、これらの診断結果は、あくまで自己理解を深めるための一つの「切符」として捉え、盲信しないことが賢明だと言えるでしょう。
「公式MBTI」を受けることの本当の意味とメリット

MBTI診断はどれがいいか迷ったとき、もし自己理解を深く追求したいと願うのであれば、やはり「公式MBTI」のセッションを受けることには大きな意義があります。
ネット上で手軽にできる16Personalitiesとは一線を画し、公式MBTIは、認定ユーザー(有資格者)による対面でのフィードバックが必須とされています。このフィードバックこそが、MBTIの真髄であり、最大のメリットをもたらす部分なのです。
では、このフィードバックセッションでは具体的に何が行われるのでしょうか。単に診断結果を教えてもらうだけでなく、「エクササイズ」と呼ばれる体験型のワークが用意されています。
例えば、感覚機能(S)と直観機能(N)のグループに分かれて同じ課題に取り組むと、驚くほどタイプごとの違いが如実に現れるそうです。このような体験を通して、参加者は自分と他者の違いを肌で感じながら理解を深めることができます。
そして、Web検査の結果に囚われず、最終的に最も「シックリくる」性格タイプを自分自身で「自己選択」する機会が与えられます。この「自己選択」こそが、MBTIが単なる分類ツールではなく、「キャラクター(持って生まれた元来の性格)を示すことのできる唯一の検査」と言われる所以でもあります。
公式MBTIを受けることのメリットは多岐にわたります。まず、自己理解が格段に深まります。人は往々にして「自分がされて心地よい関わり」を、他者にも「良かれと思って」行いがちですが、MBTIを通じて、それが必ずしも正しいとは限らないという事実に気づき、愕然とすることもあるでしょう。
これまで「間違い」だと思っていた自分の特性が、単なる「違い」であったと認識できるようになることは、自分自身をより深く受け入れ、可能性を広げる大きなきっかけとなります。
さらに、他者理解も深まることで、人間関係が大きく改善される可能性があります。特にビジネスシーンにおいては、その価値は計り知れません。
例えば、MBTIの知識があれば、相手に最も響くフィードバックの方法や褒め方、動機付けしやすい言葉が分かるため、一人ひとりの持ち味を最大限に活かすマネジメントが可能になります。
チームビルディングにおいても、これまで不快に感じていた相手の言動が「ただの違い」だと捉え直せるようになり、関係性が劇的に改善されるケースも少なくありません。
営業シーンにおいても、相手が「聞きたいこと」を伝えるために、自身の営業資料や伝え方を相手のタイプに合わせて調整する視点を得ることができます。
このように、公式MBTIは、表面的な分類に留まらず、深い自己探究と他者理解を通じて、個人が持つ無限の可能性に改めて目を向け、その持ち味を最大限に活かすための強力なメソッドなのです。
MBTIと16Personalities、どちらを選ぶべきか?

「MBTI診断 どれがいい?」と悩んだとき、結局のところ、どちらの診断テストを選ぶべきなのでしょうか。この選択は、あなたが診断に何を求めるかによって大きく変わってきます。
もしあなたが、無料で手軽に自分の性格タイプを知り、友人や同僚とのちょっとしたコミュニケーションのネタにしたり、SNSで話題を共有したりしたいのであれば、16Personalitiesのような無料のウェブ診断ツールで十分に楽しめるでしょう。
K-POPアイドルが発信源となり、韓国から日本へ広まったブームも、この手軽さから生まれたものです。自分のタイプや、推しと同じタイプを見つけることで共感し、楽しむという目的であれば、16Personalitiesは非常に有効なエンターテイメントツールと言えます。
質問数も多くなく、直感でサクサクと答えられるため、あっという間に結果が出るのも魅力です。
一方で、もしあなたが、自分自身の性格や特性をより深く理解し、それを人生やキャリアに真剣に活かしていきたいと考えるのであれば、正式なMBTIのフィードバックセッションを受けることを強くお勧めします。
前述の通り、正式なMBTIは有資格者の下でしか受けることができず、Web検査のみで完結するものではありません。専門家によるフィードバックを通じて、自分のタイプを「自己選択」するプロセスは、単なる結果の提示とは異なり、深い洞察と納得感をもたらします。
このプロセスこそが、MBTIが「世界で最も使われている性格検査」として、自己理解や多様性の尊重に貢献している所以です。
結論として、どちらを選ぶかは、あなたの「目的」次第です。
手軽に楽しむなら16Personalities。深く自己探究し、公式な場で活用する可能性を考えるなら、正式なMBTIのセッションを検討するのが良いでしょう。
ただし、どちらの診断も結果を盲信せず、あくまで「自己理解のための一つの指標」として捉え、実体験や他者との対話を通じて、自分自身の「言葉」で性格を表現し、常に成長していく姿勢が最も大切であることを忘れないでください。
MBTIの誤解と社会への影響

「MBTI診断 どれがいい?」という問いの背景には、MBTIが現代社会に与えている影響の大きさが伺えます。特に、インターネットやSNSの普及により、MBTIや16Personalitiesといった性格診断が瞬く間に広がり、その結果、様々な誤解や社会的な影響が生じています。
まず大きな誤解は、MBTIが「性格の良し悪し」や「能力の高低」を測るものであるという認識です。
無料診断ツールで自分のタイプが「○○型だから良い・悪い」「他のタイプと相性が良い・悪い」「こういう仕事は向いている・向いていない」などと信じ込まれているケースが多く見られますが、正式なMBTIは、あくまで個々人の性格の「違い」を示すものであり、特定のタイプが良い・悪いということはありません。
全てのタイプに価値があり、全てのタイプが可能性に溢れているという考え方が、MBTIの根底にあります。
このような誤解は、特に若者の間で顕著です。
MBTIが10代から20代を中心にブームとなっている背景には、「アイデンティティが不安定な時期に、何かに頼りたい」という心理があると考えられています。
自分自身を言葉で表現することが難しいと感じる中で、診断テストが自分の感情や性質を言語化してくれるツールとして求められているのです。SNSで自分のタイプをシェアし、共感を得ることで自己顕示欲や承認欲求が満たされるという側面もあります。
しかし、その手軽さと流行の裏には、深刻な社会問題も潜んでいます。
例えばアルバイトの募集要項に「〇〇タイプの人は受け入れません」と書かれたり、企業が採用スクリーニングにMBTI診断結果を活用したりする事例が報告されています。これは、MBTIの開発元が「採用、スクリーニング、人生の決定を左右するために使用されるべきではない」と明確に警告している、テストの「誤用」にあたります。企業が流行に乗り、16PersonalitiesをMBTIだと誤解して導入した結果、社内で混乱を招いているという話も耳にするようです。
さらに、インターネットの検索候補に「〇〇タイプ 性格が悪い」「空気が読めない」といったネガティブな表現が表示されることもあり、もし自分がそのタイプだった場合、深く傷つく可能性もあります。タイプ論に基づいた診断テストが流行すると、結局は誰かが優越感を持ち、誰かが劣等感を抱く構造が生まれやすいと指摘されています。
本来、MBTIは個人の専門性を重視し、じっくりと取り組める環境や、自由な発想を重視する企業文化との適合性をアピールするために活用できる可能性も秘めています。しかし、安易に結果を鵜呑みにしたり、人をタイプで判断したりすることは、人間関係を良くしようという努力を放棄する見方にも繋がりかねません。
診断結果は、あくまでコミュニケーションのきっかけや、自己分析の一助として捉え、過信せずに利用することが肝要です。情報過多の現代において、自分自身で体験し、言葉を知り、自分を表現する力を養うことこそが、本当に「自分を知る」ための道だと言えるでしょう。
「MBTI診断どれがいい?」タイプ別ランキングとあなたの可能性
- 日本人に多いMBTIタイプから見る日本の文化
- 「性格が悪い」と言われるMBTIタイプは本当に”悪い”のか?
- 「性格が良い」と評価されるMBTIタイプが持つ魅力
- MBTI診断結果を転職・キャリアに戦略的に活かす方法
- 診断結果はあなたの「可能性の設計図」である
日本人に多いMBTIタイプから見る日本の文化

「MBTI診断 どれがいい?」と多くの人が関心を持つ中で、日本におけるMBTIタイプの分布は、興味深い文化的な側面を映し出しています。
2023年の最新データによると、日本で最も一般的なMBTIタイプはINFP-T(仲介者)で12.91%を占め、次にENFP-T(運動家)が8.48%と続いています。これは世界の平均的な割合とは異なり、日本独自の文化や社会環境が影響していると考えられます。
日本の社会は、古くから「協調性」や「集団主義」を非常に重視する文化が根付いています。これは、MBTIの4つのカテゴリのうち、「判断の基準」を表すT(思考型)とF(感情型)の傾向に特に顕著に表れています。
多くの日本人がF型(Feeling、感情型)の性格を持っているとされており、これは感情や価値観を重視し、他者との調和を求める傾向が強いためだと考えられます。
ESFJ(領事官)やENFJ(主人公)といったタイプは、他人をサポートし、チーム内の調和を重んじる傾向が強く、日本の職場や学校、家庭で高く評価されやすいでしょう。
また、日本人は一般的に「義務感」と「忍耐力」が強いとされています。これは、詳細に注意を払い、実用的で専門的なスキルを持つISTJ(管理者)やISFJ(擁護者)といったタイプに多く見られる特徴です。
これらのタイプは、決められたルールを守り、正確な業務遂行を徹底するため、日本の企業文化や社会全体で高く評価される傾向にあります。
さらに、日本では「間接的なコミュニケーション」が好まれる文化があります。この点でも、感情型(F)の性格タイプは、他人の感情やニュアンスを読み取るのが得意であるため、日本の社会に適応しやすいと言えるでしょう。
一方で、T型(思考型)の人も、論理的かつ客観的な判断を重視するため、ヒエラルキーが厳格な日本社会においても、組織内での協力関係や効率的な役割を果たすことができます。
MBTIの男女比を見ると、女性はE(外向型)、F(感情型)、J(判断型)の可能性が高く、男性はI(内向型)、T(思考型)、P(知覚型)の可能性が高いという結果も出ています。これは、社会的な役割や期待が個人の性格傾向に影響を与えている可能性を示唆しています。
このように、日本におけるMBTIタイプの割合は、単なる統計データに留まらず、日本の文化や社会構造、そして人々の行動様式との密接な関係を示していると言えるでしょう。
自己のタイプを知ることは、このような文化的な背景の中で、自身の持ち味をどのように活かし、他者とより良い関係を築いていくかを考える上で、貴重な示唆を与えてくれるはずです。
「性格が悪い」と言われるMBTIタイプは本当に”悪い”のか?
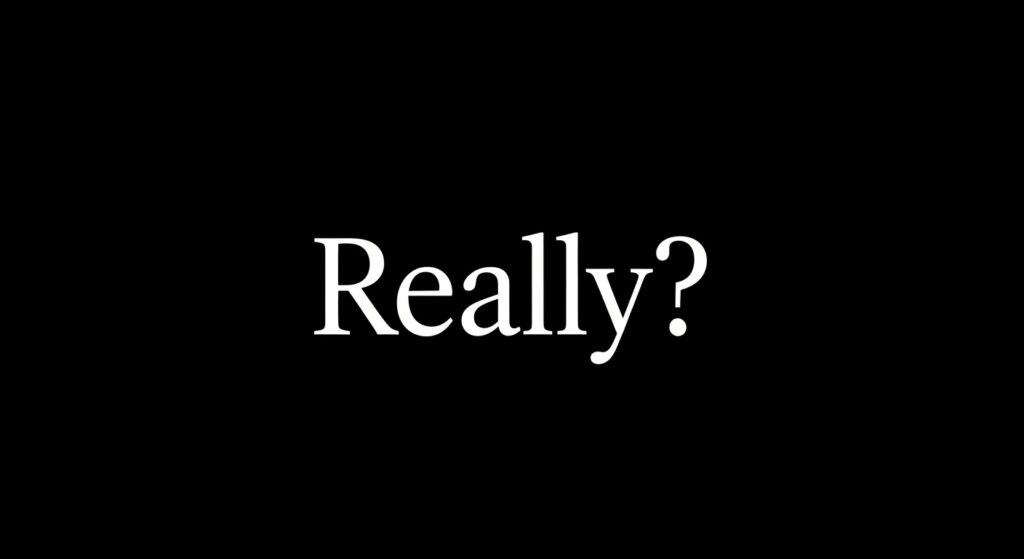
「MBTI診断 どれがいい?」と検索する人の中には、「性格が悪いMBTIタイプ」といったランキングを目にして、不安を感じる方もいるかもしれませんね。
実際に、インターネット上にはMBTIタイプを「性格が良い/悪い」と評価するランキングが存在し、ESTJ(幹部)が1位、ENTJ(指揮官)が2位、ESTP(起業家)が3位とされることが多いようです。
しかし、これらのランキングはあくまで「一般的な見解」や「特定の行動傾向」に基づいたものであり、特定のMBTIタイプが本当に「性格が悪い」わけでは決してありません。
MBTIの本来の目的は、個々人の「違い」を理解することにあります。各タイプには独自の強みと弱み、そして「ダークサイド」と表現されるような、周囲から誤解されやすい特性が存在するだけなのです。
例えば、1位とされるESTJは、外向的で思考的、判断的なタイプで、秩序や規律を重んじ、責任感や決断力に優れています。しかし、その特性が「頑固で自己中心的で威圧的」と見なされたり、感情よりも論理を優先するため「冷淡で無神経」と捉えられたりすることがあります。彼らは伝統や慣習を尊重するため、変化への抵抗感が強く、「保守的で柔軟性がない」と評価されることもあります。
2位のENTJも、外向的で直感的、思考的、判断的なリーダータイプで、カリスマ性と自信を兼ね備え、目標達成のために突き進む特性があります。しかし、「自分の考えが正しいと思い込み、他人の意見を軽視する」、「他人の感情を無視する」、「自分のルールや基準を押し付ける」といった側面が、「性格が悪い」と見なされる理由となることがあります。
3位のESTPは、現実的で行動力があり、冒険好きなタイプです。状況に応じて柔軟に対応し、人との交流も得意なムードメーカーです。しかし、「計画性や規律性に欠ける」、「無責任・自己中心的に見える」、「衝動的・無鉄砲に見える」といった点が、周囲に誤解を与える原因となることがあります。
これらの特性は、そのタイプの「弱み」や「課題」として現れるものであり、「性格が悪い」と決めつけるのは本質的ではありません。
例えば、ESTJの「頑固さ」は「強い信念」の裏返しであり、ENTJの「冷徹さ」は「客観的な判断力」の表れ、ESTPの「衝動性」は「素早い行動力」の源泉とも言えます。
大切なのは、これらの「誤解されやすい特性」を認識し、それに対する「解決策」を講じることです。
例えば、ESTJは他者の意見や感情を尊重し、感情表現を心がけ、変化に対応する柔軟性を持つことで、人間関係を改善できます。ENTJは他者の視点を尊重し、感情を理解し、ルールを柔軟にすることで、協調性を高めることができるでしょう。ESTPは計画性や責任感を意識し、衝動をコントロールすることで、より建設的な行動が可能になります。
結局のところ、「性格が悪い」という評価は、そのタイプの行動が他者との相性や期待と合わない場合に生じる「個人差」に過ぎません。自分自身の強みと弱みを理解し、それを意識しながら他者とコミュニケーションを取ることが、周囲と上手く関わるための最も重要なポイントです。
MBTIランキングは、あくまで自己理解の一助として活用し、他者を安易に「悪い」とレッテル貼りするのではなく、多様な個性として受け入れる視点を持つことが大切です。
「性格が良い」と評価されるMBTIタイプが持つ魅力
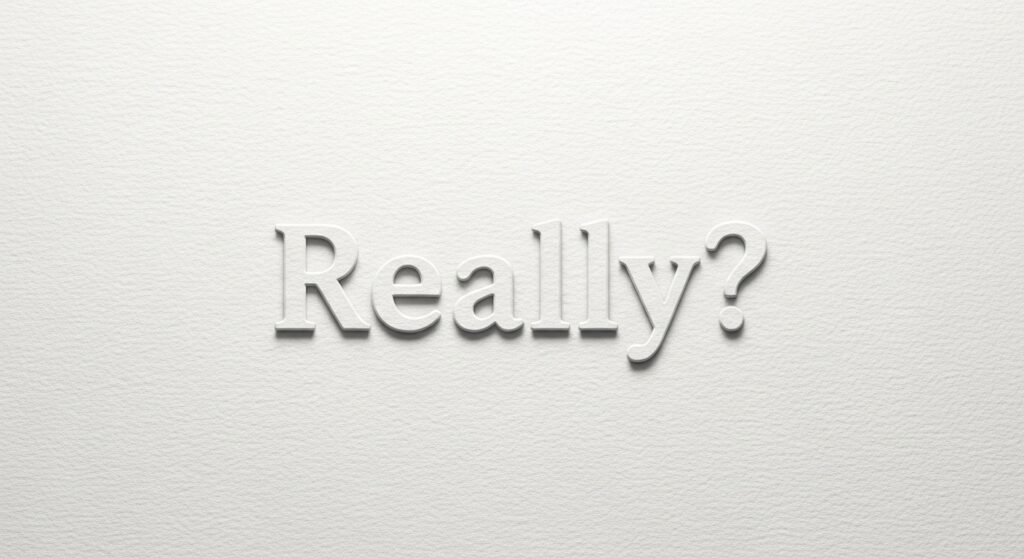
「MBTI診断 どれがいい?」とタイプを探求する中で、「性格が良い」とされるタイプに憧れを抱く人もいるかもしれませんね。
インターネット上には、「性格が良いMBTIランキング」も存在し、INFJ(提唱者)が1位、INFP(仲介者)が2位、ENFJ(主人公)が3位、ENFP(広報運動家)が4位と続く傾向があるようです。これらのタイプは、一般的に他者への配慮や共感力、協調性が高いと評価されることが多いです。
では、これらのタイプが「性格が良い」と見なされるのは、具体的にどのような魅力があるからでしょうか。
1位のINFJ(提唱者)は、洞察力、計画性、そして他者への深い配慮を持つタイプです。彼らは他人の感情に対する理解が深く、独自で正確な思考を持っています。人の可能性を見抜き、成長をサポートすることに喜びを感じるため、カウンセラーや研究職、ライターなど、人の内面に寄り添う職業にも適性があります。その深い感情理解と独自の視点が、INFJを多くの人にとって非常に魅力的な存在にしていると言えるでしょう。
2位のINFP(仲介者)は、日本で最も多いタイプとしても知られており、感受性が強く、人の感情を読みすぎて疲れやすいという側面も持ちます。しかし、彼らは自分の利益を顧みず大義のために手を差し伸べるという詩的な一面も持っています。共感力が高く、連携や調和を重視するため、周りの人の気持ちに寄り添い、聞き役に回ることで信頼関係を築きます。
3位のENFJ(主人公)は、理想的で情熱的、影響力があるタイプです。彼らは優れたコミュニケーション能力と感受性を持ち、自分のビジョンや価値観に従って行動します。他人の成長や幸せを支援するメンターのような存在であり、その優しさや思いやりが多くの人を惹きつけます。
4位のENFP(広報運動家)は、明るく社交的で、ポジティブなエネルギーが周囲の人々に良い影響を与えるタイプです。創造性、柔軟性、そして人を巻き込む力に優れており、多様な人々と協力して新しい価値を創造することが得意です。彼らの自由奔放な性格と場の雰囲気を重視する姿勢が、多くの人々を惹きつけ、愛される理由となっています。
これらのタイプが持つ特徴は、確かに社会生活においてポジティブに評価されやすいものです。
しかし、重要なのは、MBTIが性格に優劣をつけるものではないという基本原則です。各タイプにはそれぞれ独自の強みと魅力があり、その多様性こそがMBTIの面白さなのです。
例えば、論理的思考に長けたタイプや、現実的で行動力のあるタイプも、それぞれ異なる形で社会に貢献し、素晴らしい魅力を発揮します。
「性格が良い」という評価は、多くの場合、そのタイプの持つ「他者との調和」や「共感性」といった側面が、社会的に望ましいとされる傾向と合致しているために生まれるものです。
診断結果は、自己理解を深め、自身の持ち味を認識するための一つの手がかりとして活用し、決して「性格が良い/悪い」というレッテル貼りのために使うべきではありません。
全てのタイプに価値があり、それぞれの個性が輝く場所があることを理解することが、MBTI診断を真に有意義なものにする鍵となるでしょう。
MBTI診断結果を転職・キャリアに戦略的に活かす方法

「MBTI診断 どれがいい?」と真剣にキャリアを考える皆さんにとって、性格診断の結果は、単なる好奇心の対象以上のものとなり得ます。
診断結果を正しく、そして戦略的に活用できれば、転職活動における強力な差別化要素となると指摘されています。
企業の人事担当者は、客観的なデータに基づいた自己分析を高く評価する傾向があるため、診断結果を効果的に用いることで、転職の成功に大きく貢献できる可能性があります。
診断結果をキャリアに活かすには、以下の5つのフェーズで体系的にアプローチすることが重要です。
- 診断結果の深掘り分析: 診断結果を表面的に受け取るだけでなく、その背景にある理論や自分の特性を多角的に分析します。例えば、MBTIはユングの心理学的タイプ論に基づくものであるため、その理論を理解することで、より深い自己洞察が得られるでしょう。
- 強みと課題の具体化: 診断結果から導かれる強みを、転職市場で評価される具体的なスキルや能力に「翻訳」することが重要です。単に「INTJ型です」と言うだけでなく、「INTJの長期的視点と戦略的思考を活かし、5年後のビジョンから逆算して施策を立案できます」といったように、企業にもたらす価値を具体的に示すことが求められます。また、課題となる点も明確にし、改善への取り組みを示すことで、成長意欲をアピールできます。
- 職種・業界選定への反映: 診断結果に基づいて、自分に適した職種や業界を戦略的に選定します。例えば、INTJ型なら戦略コンサルタントやシステムアーキテクト、ENFP型なら人事や広報・マーケティングなど、自分の特性が最大限に活かせる分野を選ぶことで、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的なキャリアの成功に繋がりやすくなります。
- 転職活動での活用: 職務経歴書、面接、企業選択など、転職活動の各段階で診断結果を効果的に活用します。
- 応募書類: 自己PR欄で「診断ツール名+結果 → 裏付けエピソード → 数値的成果 → 企業への貢献」の構造で具体的に記載します。志望動機では、自身のタイプが企業の理念や文化とどのように合致するかを具体的に示すことができます。
- 面接: 自己紹介や強みに関する質問で、診断結果と具体的なエピソードを結びつけて説明すると説得力が増します。複数の診断で一貫した結果が出ていることを伝えるのも信頼性を高めるでしょう。
- 企業選択: 企業文化と自分の診断結果のマッチングを重視し、裁量権の大きさやチームワークの活発さなど、自身のタイプに合った環境を選ぶためのフィルターとして活用できます。面接での逆質問で、自身の診断タイプを踏まえ、企業が社員のスキルアップやキャリア開発についてどのようなサポート制度があるかなどを尋ねるのも効果的です。
- 継続的なキャリア発展: 転職後も診断結果を活用し、職場適応、昇進、キャリアチェンジに役立てていきます。診断結果は「固定的なもの」ではなく**「現在の状態を示すもの」**として捉え、定期的に見直すことで、変化する自身の価値観や適性に対応した柔軟なキャリア設計が可能になります。
ただし、MBTIは「能力」を測るものではなく「好み」を示すものであるため、診断結果だけで仕事の向き不向きを断定するのは避け、あくまで適応力を示すツールとして利用することが重要です。
診断は、あなたの可能性を最大限に引き出すための「設計図」ですが、実際にその設計図を行動に移すのはあなた自身です。
診断結果はあなたの「可能性の設計図」である
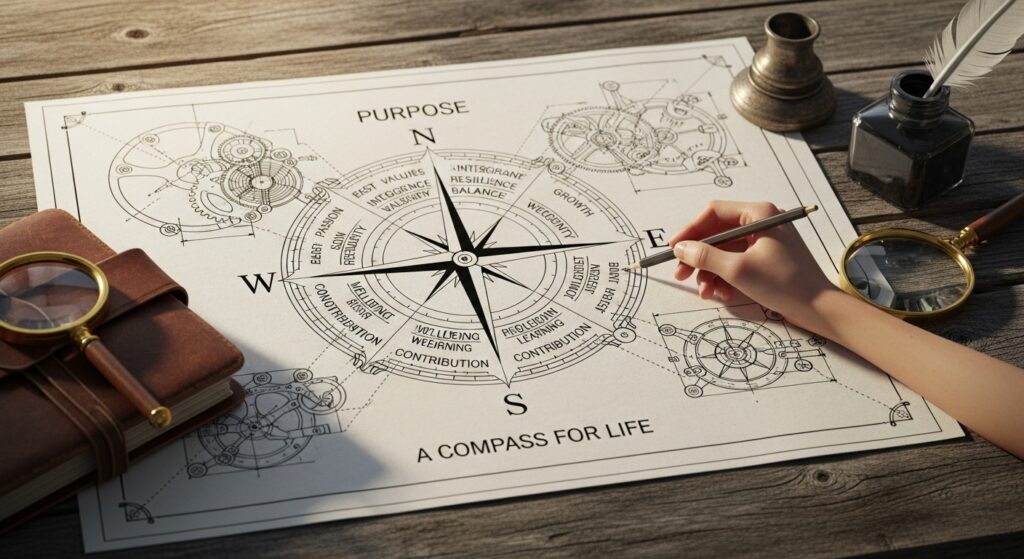
MBTI診断で性格診断を試すことは、自分自身を理解しようとする素晴らしい一歩です。
しかし、これらの診断結果は、決してあなたを固定的な「型」にはめ込むものではなく、あなたの持つ無限の「可能性」を示す「設計図」だと捉えるべきです。
MBTIの生みの親であるイザベル・マイヤーズは、MBTIが示すのはあくまで性格の「違い」であり、性格の良し悪しや能力の高低を測定するものではないと強調しています。残念ながら、手軽なウェブ診断が普及したことで、多くの人が「自分は○○というタイプだから、これが得意で、これは苦手だ」と、自分の可能性に見切りをつけてしまったり、本来持っている持ち味に蓋をしてしまったりするケースが後を絶ちません。
しかし、MBTIの根底にあるのは、「全てのタイプに価値があり、全てのタイプが可能性に溢れている」という考え方です。
診断結果は、あなたがどのような傾向を持ち、どのような状況で強みを発揮しやすいかを示唆するものであって、あなたの未来を限定するものではありません。むしろ、自分のタイプを知ることで、その持ち味を最大限に活かす方法を知り、新たな可能性に目を向けることができるのです。
人生において、人は様々な経験を通じて成長し、新たな強みを発見します。診断結果は、あくまで「現在の状態」を示すスナップショットであり、固定的なものではありません。20代前半では自己理解と基盤づくりにMBTIを活用し、20代後半ではスキル診断で専門性を確立、30代ではEQ診断でリーダーシップ能力を向上させるなど、キャリアの各段階で診断結果を定期的に見直すことで、変化する自分に合ったキャリア戦略を立てることができます。
また、診断結果が示す弱点や低い評価だった項目も、適切に対処すれば強みに転換する機会となります。例えば、コミュニケーション能力が低いと診断されても、話し方教室に通うなどの具体的な努力を示し、その成果を伝えることで、成長意欲と問題解決能力をアピールすることができます。
私たちは「自分がされて心地よい関わり」を、他者にも「良かれと思って」行いがちですが、MBTIを通じて「違い」を知ることで、これまで「間違い」だと思っていたことが、ただの「違い」だと気づけるようになるでしょう。この気づきは、自分の可能性を再認識し、他者のことももっと愛せるようになるきっかけとなります。
診断結果は、「人生という壮大な旅の切符」に過ぎません。旅の果実(自分のタイプや可能性)は、最終的に自分自身で選択し、切り開いていくものです。性格診断に頼りすぎるのではなく、人との対話や様々な挑戦を通じて「できる・できない」「合う・合わない」を身をもって判断し、自分自身の言葉で感情や性質を表現する力を養うこと。
これこそが、あなたの「可能性の設計図」を最大限に活かし、理想のキャリアと人生を掴み取るための本当の鍵となるでしょう。
総括:「MBTI診断どれがいい?」あなたの探求を深めるための鍵
この記事のまとめです。
- 正式なMBTIは有資格者によるフィードバックが必須であり、16Personalitiesは無料で手軽にできる模倣品である
- 16Personalitiesは占い的に楽しむ分には問題ないが、公式MBTIと混同し誤用すると混乱を招く可能性がある
- MBTIは性格の良し悪しや能力の優劣を測るものではなく、あくまで個人の「違い」を示すツールである
- 科学界からはMBTIの信頼性(テスト-再テスト信頼性や二分法)に多くの批判がある
- MBTIを支持する研究には運営団体によるものが多く、独立性が疑問視される
- 企業がMBTIを人材のスクリーニングや採用に利用することは、その開発元自身も不適切と警告している
- MBTIの本来の目的は、深い自己理解と他者理解を促し、個人の可能性を広げることにある
- 認定ユーザーによるフィードバックでは、体験型ワークを通じて自分と他者の「違い」を体感し、自己選択でタイプを決定する
- MBTIの理解は、マネジメント、チームビルディング、営業といったビジネスシーンでのコミュニケーション改善にも役立つ
- 日本人に最も多いMBTIタイプはINFP-Tであり、日本の協調性や集団主義文化がF型の傾向に影響を与えていると考えられる
- 「性格が悪い」とされるMBTIタイプ(ESTJ、ENTJなど)も、本来は特定の強みが過剰に現れた「違い」であり、性格自体が悪いわけではない
- 「性格が良い」とされるMBTIタイプ(INFJ、INFPなど)は、共感性や協調性といった特性が社会的にポジティブに評価される傾向にある
- 性格タイプに関するランキングはあくまで参考であり、全てのタイプに価値があり、優劣は存在しない
- MBTI診断結果は、転職活動において自己分析を深め、自身の強みを具体的なエピソードと結びつけて戦略的にアピールする「武器」となりうる
- 診断結果は固定的なものではなく、経験や成長によって変化する「可能性の設計図」であり、定期的な見直しと実体験による自己探求が重要である


